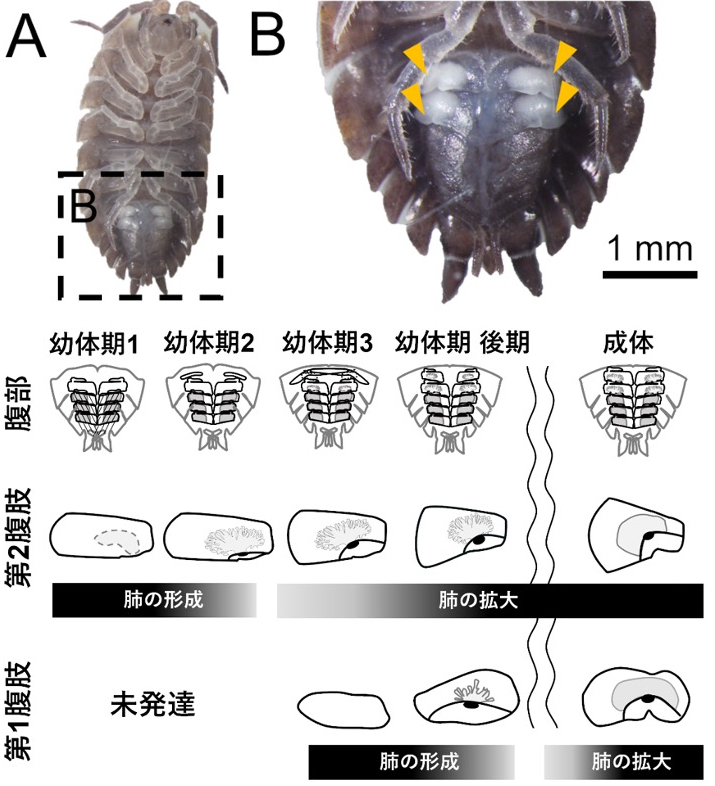第302回の「三崎談話会」の開催が決まりましたのでご連絡いたします。今回は対面とオンラインのハイブリッドでの開催を予定しております。参加ご希望の方は、下記のGoogleフォームでご回答下さい。zoom URL等の情報が返信されます。皆様のご参加をお待ちしております。
【第302回 三崎談話会】
日時:2023年6月15日(木) 13:00〜
場所:東京大学三崎臨海実験所 教育棟講義室
(zoomでもセミナーの模様を配信致します。)
参加申込:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdss6BKzJZ0Yf9P9AqX9UprgYKfem-FljwslrutYGpu414Nbw/viewform
「寄り戻しても前の関係には戻られへん:頭足類の系統進化からみる貝殻進化 」
Davin H. E. SETIAMARGA / デフィン・スティアマルガ
(和歌山工業高等専門学校生物応用科学科)
頭足類(頭足動物綱)は約800種からなる軟体動物門の一つの分類群である。系統的に貝殻亜門に分類されるが、オウムガイ(オウムガイ亜綱)以外の鞘形亜綱に含まれるほぼ全ての現生の記載種には貝殻が退化している。また、腹足類や二枚貝と異なり、頭足類はその長い進化史を通じて、その棲息環境は海に留まっている。本発表ではまず、頭足類の系統樹及び分岐年代推定によってその多様性変化と地質年代に起きた環境変動との関連性について議論する。記載現生種数の約2割で全亜科の全てを網羅する合計164種のミトコンドリアゲノムを用いた系統ゲノム解析と分岐年代推定からは、頭足類蛸形亜綱の現生種は約7100万年前から多様化し、白亜紀後期ごろに種分岐を繰り返したことがわかった。これは、大陸の分裂や火山活動が原因となった地球温暖化などが新しいニッチを作り、放散の原因になったと推測できる。次いで、様々軟体動物の貝殻マトリックスタンパク質(SMPs)及びゲノム情報の比較や胚発生時の発現パターンから、祖先的で生きた化石とされているオウムガイの貝殻は軟体動物のそれと分子レベルにおいても相同的であることが示唆された。一方で、私たちが行ったミトコンドリア系統ゲノム解析や形態形質による分類からも、貝殻が全くないムラサキダコ類と単系統な姉妹関係になっているカイダコ類には、オウムガイや絶滅種であるアンモナイトの貝殻に形が酷似してカルサイトからなる「卵鞘」がある。行動観察によって、外套膜ではなく第一腕によって作られるこの卵鞘は貝殻の相同器官ではないとされてきたが、その物的証拠はなかった。そこで私たちは、卵鞘に含まれているタンパク質(卵鞘マトリックスタンパク質;EcMP)の特定および様々な軟体動物のSMPsとの比較解析を行なった。その結果、比較した全ての種に共通しているものはなかったが、一部の貝殻亜門動物のSMPsとだけ共通しているEcMPsもあったことが明らかになった。このことは、カイダコ類が卵鞘を形成するために、貝殻亜門のSMPs以外のタンパク質をリクルートする一方で、いくつかのSMPs、特に石灰化に関連するとされる遺伝子を再リクルートしていることが示唆された。これは、カイダコ類における卵鞘形成は、複数の貝殻亜門のSMPsを再リクルートすると同時に、本来殻形成に関係のない多くのタンパク質をリクルートすることで獲得されたと考えている。即ち、一度別れた恋人とより戻しても別れる前と全く同じ関係に戻ることができないのと同様に、カイダコ類の卵鞘は形や構造、形成に使われている遺伝子や組成が貝殻のそれらの一部のみ似通っており、完全な相同器官ではないのである。